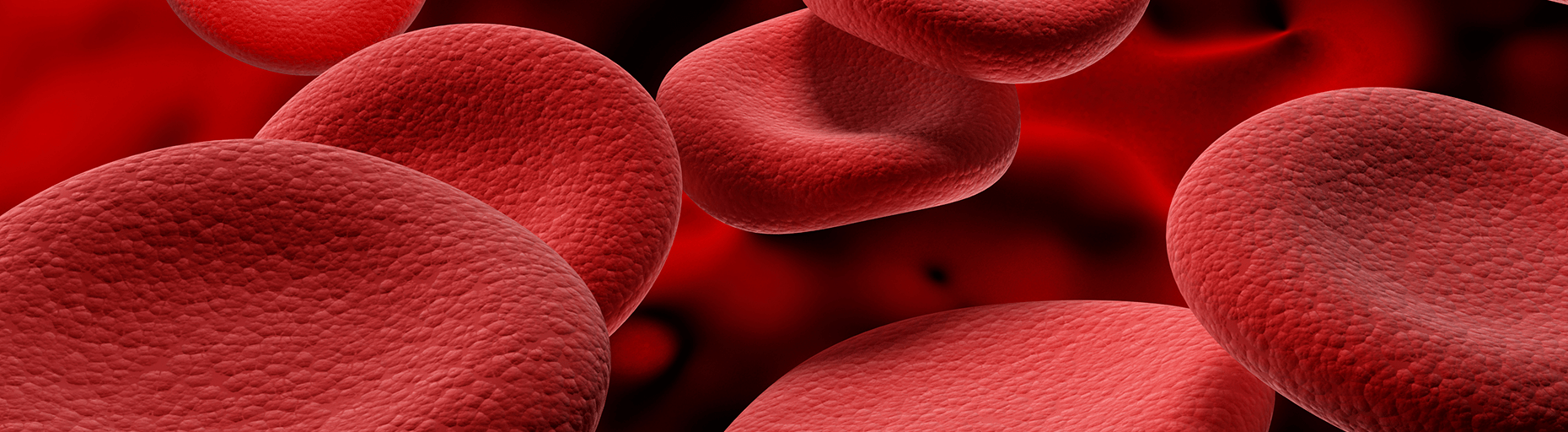英文タイトル: Brilliant Ideas that Turned the History
「逆転の発想」は医学や医療と限らず、社会面でも重要なアプローチでしょうが、呼吸器領域のを探してみました。純粋の医学の面や薬物使用の面にもあるに相違ありませんが、私がみつけたのはいずれも技術的な内容です。
陰圧開胸から陽圧式人工呼吸による開胸
1900年初頭の時点で、当時医学面で先行していたドイツにおいて「陰圧開胸」が開発されました。これはComroe 氏の Retrospectroscope に詳しく説明されており、この記事は現在無料で公開されています。(http://www.thoracic.org/sections/about-ats/centennial/retrospectroscope/index.html およびhttp://www.thoracic.org/sections/about-ats/centennial/retrospectroscope/articles/resources/8-Inflation-1904Model.pdf )。
今から考えれば実にバカげたことですが、「胸腔内は陰圧だから、開胸すると肺が虚脱してしまう。それを防ぐには患者の頭側を平圧にして開胸部分を陰圧に保てばよい」というので、手術室を陰圧にしてその中で手術をしたというのです。主張して実行したのがドイツ外科学会の大立て者であったザウエルブルッフだったので、急速に広まりました。当時、すでに気管挿管が開発されて一部の状況や施設では利用されていましたが、一つは主唱者の威力と、もう一つはそれなりに手術が可能だった故、この手法はしばらく勢力を保ちました。1910年代には第一次世界大戦があり、戦場の方法としては陰圧室などは実際的でなくてむしろ気管挿管による陽圧換気が使われましたが、それでも戦後になってもこの趨勢は一挙には衰えませんでした。
日本ではさらに遅れています。気管挿管自体がほとんど普及していなかった故もありますが、大正の終りから昭和の始め頃の状況を検討した藤田俊夫氏の文章(http://www2.kpu-m.ac.jp/~anesth/1959.html) によると、日本外科学会は"異圧開胸か平圧開胸か"という大論争があり、「陽圧をかける必要はない、平圧で肺がつぶれても大丈夫」という意見で決着したということです。類似のことを、桑江千鶴子氏も述べています。(http://ameblo.jp/kempou38/entry-10157178103.html)
ところで、この「気管挿管による開胸手術」を「逆転の発想」と呼ぶのは妥当でないでしょう。陰圧室での開胸というバカげた事柄と比較すれば、次第に普及してきた気管挿管を利用するのは実に素直で、むしろ陰圧室での開胸のほうを「おろかな逆転の発想」と呼ぶのが妥当と感じます。
鉄の肺から気管内陽圧による呼吸管理へ
次も換気法で、やはり同様に「陰圧換気」から「陽圧換気」への転換です。鉄の肺は、1929年にDrinker が発明したとされますが、製作自体はもっとさかのぼってすでに19世紀に報告があります。Drinker はこれを商品化し、1930年代から蔓延したポリオで呼吸麻痺のおこった患者に早速使う道を開き、一部では費用と供給不足によって類似品を木造した場合もあります。
その「鉄の肺による呼吸管理」が、現在の陽圧換気タイプに移行するには明確なきっかけがあります。それまでも、鉄の肺の不足な時点で「気管挿管による陽圧換気」で急場を切り抜けた例が散発的にあったようですが、1951~52年にコペンハーゲンを中心に発生した大流行では、鉄の肺が極端に不足しました。窮余の策として、患者に気管挿管や気管切開をして、麻酔器などをもちいて手押しで人工呼吸しました。具体的な患者数は明らかではありませんが、三桁それも四桁にちかい人数とされています。
1955年になって、デンマークとスウェーデンのデータを解析した結果、「鉄の肺と陽圧式人工呼吸とは死亡率は双方2%で、成績自体には差はない」と判明しました。(http://medt00lz.s59.xrea.com/nippv/node2.html) なお、この記述は上記URL で「レジデント初期研修用資料」となっていますが、病院名や記述者の署名はなくて、はたして実際の病院で使われる資料なのか、「使って欲しい」という記述者の意欲なのかは不明です。しかし、内容はまじめで質もかなり高度と感じます。
ところで、この方針転換も「逆転の発想」というよりは、「仕方なく採用した方法が予想外に優れていて採用された」というのが事実に近いでしょう。
コペンハーゲンの話は患者の数が多かったので歴史的にも重要ですが、ポリオ患者を気管挿管や気管切開チューブの陽圧呼吸で維持した報告自体は、これ以前にも報告例はあります。
IMVの開発
IMV の開発は、真の意味で「逆転の発想」といえそうで、開発されたのは1971年です。
それまで、人工呼吸の際には何とかして「補助呼吸」つまり患者の自発呼吸を感知してそれを補助するタイプの人工呼吸を求めていました。せっかく自発呼吸があるのに、それを薬物や過換気などで止める努力をしており、それが「もったいない」、「良くない気がする」故です。この「補助呼吸」は、人間が手で感じながら行う場合たとえば麻酔時には十分にうまく出来たものの、ICUで装置を使う場合は困難で、感知を敏感にすると人工呼吸器がはげしく動きすぎ、鈍感にすればもちろん患者が苦しがり、結局うまくゆきません。個々の担当者が人工呼吸器のセッティングや回路を工夫し、一方人工呼吸器を製作する側もいろいろと検討しましたが、解決できないままでした。
IMVは、この「補助呼吸」の考え方をすっきりとあきらめて、その代わりに患者に「ある程度は勝手に自発呼吸させ、ときどき人工呼吸を加えて換気の不足を補い、同時に疲弊を防ぐ」やり方で、その際に「人工呼吸の動作していない時は、同じ回路で患者が自由に自発呼吸できる」という点がポイントです。このIMVには、「患者のほうが装置のIMVのタイミングにあわせるようだ」という副次的なメリットもありました。
IMVは元来小児用に開発されたものですが、最初の論文(ref 1) はPubMedに載ってはいるものの無料では読めません(http://www.anesthesia-analgesia.org/cgi/reprint/50/4/533)。もっとも、施設がこの雑誌を講読していれば全文にアクセスできるはずです。しかし、そのすぐ後に出たこのIMVをウィーニングに用いた"Chest"誌の論文(ref 2) はオープンアクセスで、こちらのほうがはるかに重要です。(http://www.chestjournal.org/cgi/reprint/64/3/331)
この頃まで、人工呼吸からのウィーニングには今で言う"on-off 法"しかなくて、「まず5分間はずし、次に10分間、20分間--と延長」して行きました。定式はなくて、患者により担当する医師によって、用心深いので進行が遅れたり、逆に強引過ぎて元の木阿弥になったり極端な場合は心停止を招いたりもしたものでした。
IMVがこの種の問題をすべて解決したわけではありません。しかし少なくとも、「安心して進行させる」ことが可能になりました。もっとも、その後「IMVではウィーニングが遅くなったり時間がかかる」というデータも出ています。(JAMA誌、1981. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/246/11/1210 抄録のみ。NEJM誌 1995. http://content.nejm.org/cgi/content/full/332/6/345 オープンアクセス) しかし、そういう批判を超えて、ウィーニングにはこのIMVとその後加わったPSV の採用が圧倒的に多くなりました。単純な「時間」や「期間」では測れない、患者の生理の安定や施行者の負担の軽減、患者と関係者の心理的要因も関係しているのは、担当者にはわかっていたことです。
パルスオキシメーター:ノイズを逆用
私の詳しい血液ガスなどの領域で何かと考えて、パルスオキシメーターに思い当たりました。このテーマを本稿に含めるに際して、インターネットの記述を探しましたが、みつかりません。しかし、発明者の青柳卓雄氏によると発想はこうです。1970頃、氏は色素希釈法による心拍出量測定の研究をしていて信号の動揺に悩まされました。色素(インドサイアニングリーン) による吸光を体外から測定しようとすると、動脈の拍動によって滑らかな信号が得られず、小さな波が乗ります。
この動脈拍動による波に悩んだ結果、逆に「この波を利用して体外から動脈の情報だけを分離採取しよう」と考えたところがまさに「逆転の発想」です。この経過は青柳氏から直接伺った他に、何かの文書にもなっていると記憶しています。
「逆転の発想」を支えるもの
最後に、「逆転の発想」を支える要素について一つ加えます。発想は重要ですが、それをものにするには実力が必要という点です。たとえば、青柳氏が血管に光をあててヘモグロビンによる吸光度を測るに際して、拍動信号は元の信号よりずっと小さいので、それをとりだして酸素飽和度として読み取るという数学と光学と工学を必要としており、それは1974年の長い抄録に載っています。さらに、その商品化にあたっては日本光電が成功せず、ミノルタが最初に成功したのは光学機器の扱いにカメラ会社の能力が優れていた故と解釈します。ところが、それさえも性能的に不満足で、世に受け入れられる商品として成功したのはディジタル技術を駆使したバイオックスやネルコアなど欧米の会社でした。つまり、試作品作成の青柳氏らの実力、商品化する山西氏とミノルタ社の実力、実用化の技術を付加した欧米の会社の実力など、それぞれが加わってはじめて「アイディアが生きた」わけです。
IMVの場合も、「人工呼吸の動作していない時は、同じ回路で患者が自由に自発呼吸できる」というそれまでにはなかった回路を作成する必要があり、それが数人の共同研究者に割りあてられたとも推測できます。そういう組織力も実力のうちと言うべきでしょう。
こんな点は歴史を考えてみれば当然で、ニュートンはリンゴが落ちるのを観察しただけではなくて万有引力と力学の法則の確立にはあの数学力があったからこそであり、アインシュタインの相対性理論は偏微分方程式だらけです。
「逆転の発想」自体は重要ですが、それをものにする学力や組織力も重要という点を指摘しておきます。
参考文献
1. Kirby RR, Robison EJ, Schulz J, DeLemos R. A new pediatric volume ventilator. Anesth Analg. 1971 Jul-Aug;50(4):533-7.
2. Downs JB, Klein EF Jr, Desautels D, Modell JH, Kirby RR. Intermittent mandatory ventilation: a new approach to weaning patients from mechanical ventilators. Chest. 1973 Sep;64(3):331-5. オープンアクセスです。